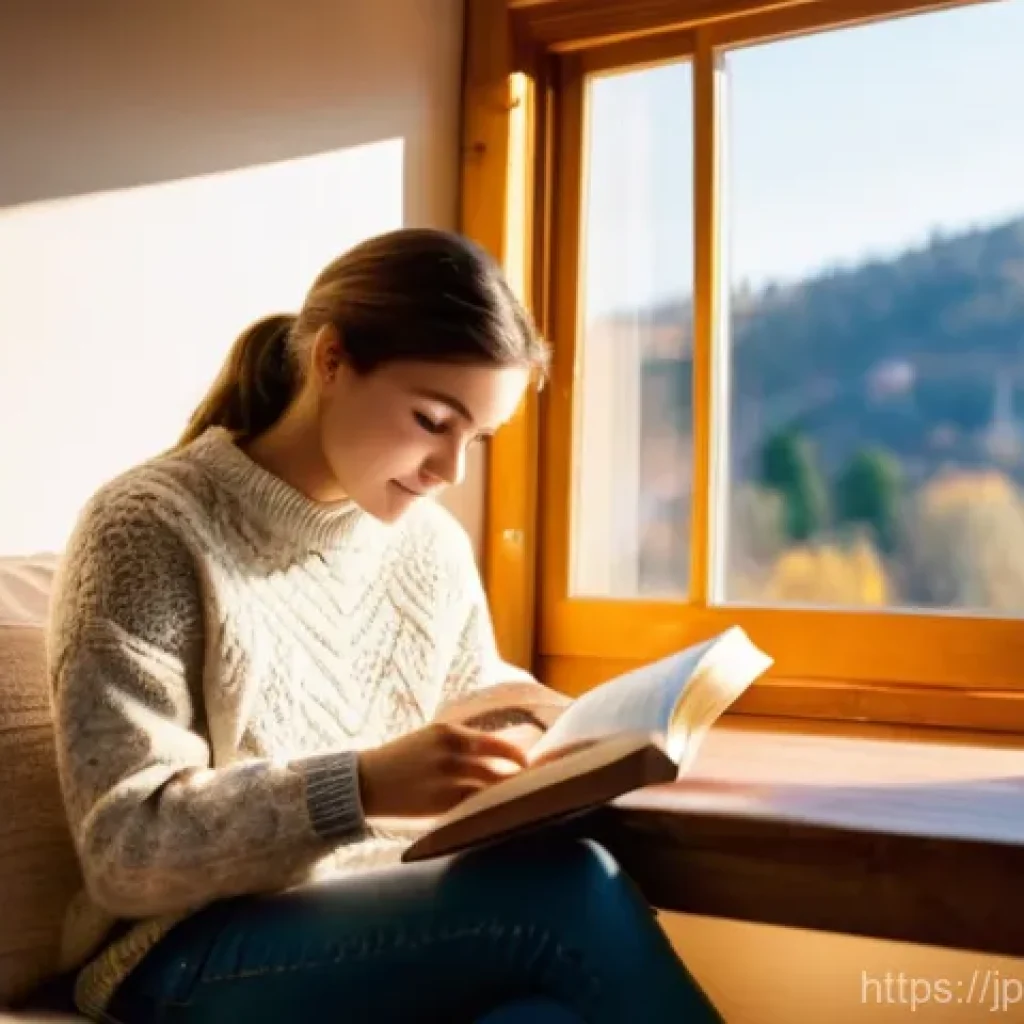ドイツ語の原書を読むって、なんだかハードルが高そう…そう感じている方も多いのではないでしょうか?私も最初は、「本当に読めるようになるのかな?」って不安でいっぱいでした。でもね、実際に一歩踏み出してドイツ語の原書を手にしてみると、その世界は想像以上に奥深く、そして楽しいんです!最近は、AIを活用した翻訳ツールや語学アプリもすごい進化を遂げていますが、それでもやっぱり原書でしか味わえない「生きたドイツ語」の魅力って、格別なんですよね。特に、今話題になっている文学作品や、ビジネスで役立つ最新の専門書なんかを原書で読むと、ただ単に言葉を学ぶだけじゃなく、その国の文化や人々の思考パターンまで肌で感じられるから、本当に新しい発見の連続なんです。私も最初は簡単な児童書から始めて、少しずつレベルアップしていったんですが、あの「わかった!」という達成感は忘れられません。単語をただ覚えるだけでなく、文脈の中で自然な表現を掴むことができるので、驚くほど会話力もグンと伸びたのを実感しています。AIでは決して教えてくれない、著者の心の動きやユーモアまでダイレクトに伝わってくるんですから。「でも、いったいどんな本から読み始めればいいの?」って迷っちゃいますよね。たくさんある中で、自分のレベルにぴったり合って、しかも「読んでて楽しい!」って心から思える一冊を見つけるのが、実はドイツ語学習を続ける上での一番のポイントなんですよ。最近は、電子書籍のおかげで手軽に原書にアクセスできるようになったり、オンラインで読書会が開催されたりと、学習を取り巻く環境も大きく変わってきています。今回は、そんなドイツ語学習者の皆さんが「これなら挑戦できる!」「もっと知りたい!」と感じるような、とっておきのドイツ語原書を、私のリアルな読書経験を交えながら厳選してご紹介しますね。さあ、あなたもこの機会にドイツ語原書の世界へ飛び込んでみませんか?このブログで、あなたの「運命の一冊」を見つけるヒントを掴んで、新しい学びの扉を大きく開いてみましょう!さあ、ドイツ語学習の次なるステップへ!具体的にどんな本がおすすめなのか、一緒にじっくり見ていきましょう!
最初の一歩!自分にぴったりのドイツ語原書を見つけよう

「よし、ドイツ語の原書を読んでみよう!」そう意気込んでも、いざ本屋さんやオンラインストアで膨大なタイトルの前に立つと、「どれを選べばいいんだろう…」って途方に暮れちゃいますよね。私も最初の頃は、背伸びして難しすぎる本に手を出しては、数ページで挫折…なんて経験を繰り返していました。でもね、これって決してあなただけじゃないんです。ドイツ語原書読解の成功の鍵は、最初の「一冊」をいかに上手に選ぶかにかかっていると、私は声を大にして言いたい!自分のレベルに合った本を選ぶこと、そして何より「読んでて楽しい!」と思える本に出会うことが、長く続ける秘訣なんです。
レベル別おすすめジャンルと選び方
じゃあ、具体的にどう選べばいいの?って話になりますよね。私の経験から言うと、まずは自分のドイツ語レベルを客観的に見極めることが大切です。例えば、まだドイツ語学習を始めたばかりのA1~A2レベルなら、いきなりゲーテやカフカに挑戦するのは無謀です。絵本や児童書、あとは語学学習者向けに優しく書き直された「多読用リーダー」から始めるのが鉄板中の鉄板!文字も大きくて挿絵があったり、語彙も限定されているから、無理なく読み進められます。少しレベルが上がってB1~B2くらいになったら、青春小説やライトノベル、あるいは短編小説集なんかもおすすめです。最近だと、ドイツのティーンエイジャーに人気のシリーズものなんかは、日常会話で使える表現がたくさん出てきて、読み物としても面白いんですよ。C1以上であれば、本格的な文学作品や専門書にも挑戦できますが、それでも興味のある分野から入るのが、モチベーション維持のコツです。私は最初、ドイツの昔話を集めたグリム童話から入りましたが、知っている物語でもドイツ語で読むと、また違った味わいがあってすごく楽しかったのを覚えています。
誰もが知る名作から始める安心感
もう一つ、選び方のヒントとして、すでに内容を知っている本から入るのもすごく効果的です。例えば、英語圏の児童書や日本のアニメのドイツ語翻訳版など。物語の筋が頭に入っている分、知らない単語が出てきても文脈で推測しやすいし、「あ、このセリフ、ドイツ語ではこう言うんだ!」という発見が楽しいんです。私も以前、大好きな宮崎駿監督のアニメ映画のドイツ語版ノベライズを読んでみたんですが、情景が目に浮かぶから、すんなりドイツ語の世界に入り込むことができました。有名どころで言えば、「星の王子さま」(Der kleine Prinz)なんかは、大人向けの哲学的な要素もありつつ、言葉遣いは比較的平易なので、多くの学習者におすすめできます。内容がすでに頭に入っているから、純粋にドイツ語の響きや表現に集中できるんですよね。この安心感が、原書読解の最初のハードルをグッと下げてくれるはずです。
原書読解を挫折させない!効果的な学習アプローチ
せっかく「この本を読むぞ!」と決めても、途中で「うーん、全然進まない…」「難しい…」ってなっちゃうこと、ありますよね。私も何度も経験しました。特に、ドイツ語の長い複合語や複雑な文構造に出くわすと、思考が停止しそうになることも。でも大丈夫!ちょっとした工夫で、原書読解は格段に楽しく、そして効率的になります。大切なのは、完璧を求めすぎないことと、自分なりの「攻略法」を見つけること。私の場合は、いくつかの戦略を組み合わせることで、以前よりもずっとスムーズに読み進められるようになりました。
辞書との賢い付き合い方、私の秘密兵器
原書を読み始めた頃は、本当に一語一句、知らない単語が出てくるたびに辞書を引いていました。でも、それだと文章のリズムが途切れてしまうし、何より疲れてしまうんですよね。そこで私が編み出したのが、「秘密兵器としての辞書活用術」です。もちろん、重要なキーワードや何度も出てくる単語はしっかり引きますが、それ以外の、文脈からおおよその意味が推測できる単語は、あえてスルーしてみるんです。最初は勇気がいりますが、意外と全体の意味は掴めるもの。そして、どうしても理解できない重要な文やフレーズが出てきたら、そこで初めて電子辞書やオンライン辞書アプリの出番です。最近の翻訳アプリはカメラで文字を読み取ってくれる機能もあるので、紙の辞書よりも圧倒的に時短になります。私の場合は、DeepLやGoogle翻訳を補助的に使いながら、どうしてもわからなかった表現だけはきちんと確認するようにしています。全てを完璧に訳そうとしない、この「割り切り」が、読書を続ける上での大きなポイントだと実感しています。
多読と精読のバランスで理解度アップ
ドイツ語の原書読解には、「多読」と「精読」という二つのアプローチがあります。多読は、辞書をあまり引かずに、とにかくたくさんの文章を読み進めることで、ドイツ語の語順や表現に慣れることを目的とします。一方、精読は、一文一文を丁寧に文法的に分析し、細部まで正確に理解することを目的とします。私が最初に挫折した理由は、全てを精読しようとしていたからです。でも、この二つをうまく使い分けることで、読書は劇的に変わります。例えば、一日に読むページ数を決めて、そのうちの最初の数ページは精読、残りは多読、といった具合です。あるいは、ある章は多読でサッと読み、特に気に入った章や重要な章だけを精読するとか。私の場合は、特に気に入ったフレーズや、ドイツ語らしい表現が出てきた箇所は、蛍光ペンでマークして後でノートに書き出すようにしています。こうすることで、ただ読むだけでなく、能動的に学習する姿勢が身につくんです。このバランス感覚が身につくと、読書のハードルがぐっと下がるだけでなく、ドイツ語そのものに対する理解度も深まりますよ。
読書がグッと楽しくなる!ドイツ語力の意外な伸び
「ドイツ語の原書を読む」って聞くと、やっぱり「しんどそう」「大変そう」というイメージが先行しがちですよね。もちろん、簡単なことばかりではありません。でも、その努力の先には、想像以上の大きな喜びと、驚くほどグッと伸びたドイツ語力が待っているんです。私も、最初は「単語を増やすため」「文法を覚えるため」という義務感から読み始めていましたが、いつの間にか「もっと読みたい!」「この世界に浸りたい!」という純粋な楽しみに変わっていきました。そして、気づけば、自分のドイツ語の表現力が格段に豊かになっていることに感動したんです。
語彙力、文法力だけじゃない!「生きた」表現が身につく感動
語学学習といえば、単語帳とにらめっこしたり、文法書をひたすら解いたり…というイメージが強いかもしれません。もちろんそれも大切ですが、原書を読むことで身につくのは、それだけじゃないんです。例えば、教科書では「こんにちは」は「Guten Tag」と習いますが、物語の中では「Moin!」とか「Servus!」みたいな、地域性のある挨拶や、登場人物の年齢や関係性に応じた様々な表現に出会えます。これこそが「生きたドイツ語」なんです!私も、ある小説を読んでいた時、「いや、ここは絶対『~てしまった』というニュアンスなんだよな」という表現に遭遇して、教科書には載っていないけど、この状況だとまさにこれだ!と雷に打たれたような感覚を覚えたことがあります。単語や文法をバラバラに覚えるのではなく、文脈の中でどのように使われているかを体験できるから、実際に自分が話すときや書くときに、スッと自然な表現が出てくるようになるんです。この感覚は、どんなに優れたAI翻訳機を使っても得られない、人間ならではの感動だと確信しています。
読書で広がるドイツ文化への理解と視野
ドイツ語の原書を読むことは、単に言語を学ぶだけでなく、ドイツという国の文化、歴史、人々の考え方に深く触れることでもあります。例えば、ドイツ文学の古典を読めば、ロマン主義や啓蒙主義といった時代の思想背景が肌で感じられますし、現代小説を読めば、今のドイツ社会が抱える問題や、人々の日常が垣間見えます。私自身、ドイツの歴史小説を読んで、それまでニュースでしか知らなかった歴史的事件が、どれだけ人々の生活に影響を与えていたのかをリアルに感じることができました。登場人物の行動原理や思想に触れることで、「あぁ、ドイツの人ってこういう考え方をするんだな」とか、「この表現の背景には、こういう文化的な意味合いがあるのか」といった発見が本当に多いんです。これは、観光ガイドブックを読んだり、表面的な情報に触れるだけでは決して得られない、深いレベルでの理解へと繋がります。読書を通して、自分の世界観や視野がどんどん広がっていくのを実感できるのは、原書読解の最大の魅力の一つだと私は思いますね。
デジタルとアナログ、賢く使い分けてドイツ語読書を加速!
最近の語学学習を取り巻く環境は、本当に恵まれていますよね。昔は分厚い紙の辞書を片手に、片っ端から単語を引いていましたが、今はスマホ一つで何でもできちゃう時代。ドイツ語の原書読解も、デジタルツールを上手に活用することで、以前よりも格段に効率的かつ快適になりました。もちろん、紙の書籍ならではの魅力も捨てがたいもの。どちらか一方にこだわるのではなく、それぞれの良いところを理解して賢く使い分けることが、読書を長く続ける秘訣です。私も、気分や状況に合わせて、デジタルとアナログを行き来していますよ。
電子書籍のメリット・デメリットと活用術
電子書籍の最大のメリットは、何と言っても手軽さですよね。KindleやiPad一台あれば、何十冊もの本を持ち歩けるし、インターネットさえあれば、読みたいと思った瞬間に新しい本がダウンロードできる。私も旅行中は、物理的な本の重さを気にせずに済む電子書籍を多用しています。そして、ドイツ語学習者にとって特に嬉しいのが、内蔵辞書機能やハイライト機能。知らない単語が出てきても、ワンタップで意味がわかるし、気になる表現をすぐにマークできるから、読書の流れを止めずにサクサク読み進められます。文字の大きさやフォントも自由に変えられるので、目の疲れを気にせず長時間読書できるのも魅力的です。ただ、デメリットとしては、紙の書籍のような「物質感」がないことや、バッテリー切れの心配がある点でしょうか。長時間画面を見続けると目が疲れることもあります。私の活用術としては、主に多読でどんどん読み進めたい時や、外出先でのスキマ時間に読む本として電子書籍を選んでいます。
やっぱり紙が好き!物理的な本の魅力と楽しみ方
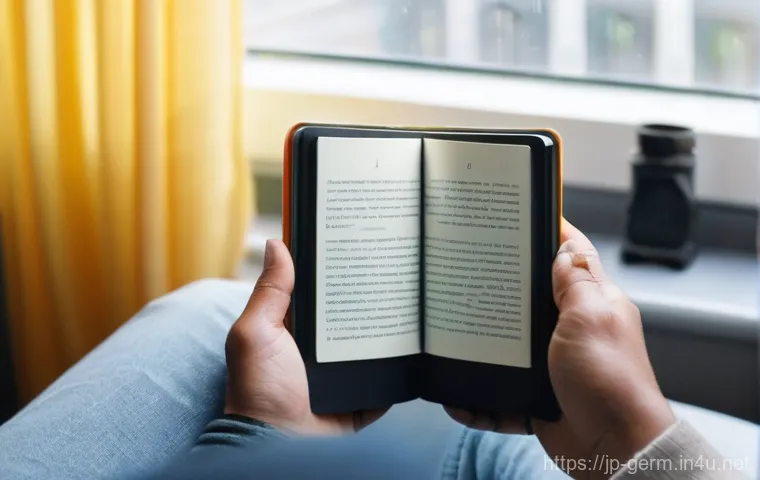
電子書籍がどれだけ進化しても、「やっぱり紙の本が好き!」という方も多いのではないでしょうか。私もその一人です。ページをめくる時の指先の感触、紙の匂い、そして本そのもののデザイン。これらは電子書籍では味わえない、物理的な本ならではの魅力ですよね。紙の書籍で読むと、文章がより深く心に染み入るような気がしますし、自分の書き込みや付箋でいっぱいの本は、まるで自分だけの学習の歴史を刻んでいるようで愛着がわきます。さらに、紙の本はバッテリーを気にすることなく、どこでも読めるという安心感もあります。私は特に精読したい時や、繰り返し読み返したいお気に入りの本は、紙の書籍を選ぶことが多いです。書店の棚から「これだ!」と感じる一冊を見つける喜びも、紙の書籍ならではの体験ですよね。
ここで、デジタルとアナログのドイツ語読書における比較を、私が個人的に感じるメリット・デメリットでまとめてみました!どちらか一方に偏るのではなく、それぞれの良さを理解して、上手に使い分けるのが賢い学習法ですよ。
| 特徴 | 電子書籍のメリット | 電子書籍のデメリット | 紙の書籍のメリット | 紙の書籍のデメリット |
|---|---|---|---|---|
| 携帯性・利便性 | 複数冊を軽量で持ち運び可能、即座に購入・ダウンロード | バッテリー切れの心配、画面がないと読めない | バッテリー不要、何処でも読める安心感 | 重くかさばる、購入に手間がかかる場合がある |
| 学習機能 | 内蔵辞書、ハイライト、検索機能が充実 | 集中力が散漫になりやすい、視覚的な情報が少ない | 書き込みや付箋で自由にカスタマイズ、集中しやすい | 辞書を引く手間がかかる、検索が難しい |
| 読書体験 | 文字サイズ調整可能、気軽に多読できる | 物質感がなく、読んだ実感が薄い場合がある | ページをめくる喜び、所有欲を満たす | かさばるため、多読には不向きな場合も |
読書仲間との出会い!コミュニティでドイツ語学習をもっと豊かに
ドイツ語の原書読解って、基本的に一人で黙々と取り組むものだから、時々「本当にこれで合ってるのかな?」「この表現、どういうニュアンスなんだろう?」って、誰かに相談したくなること、ありませんか?私も、何度か壁にぶつかって「もうやめようかな…」と思った時がありました。でも、そんな時に支えになってくれたのが、同じ目標を持つ読書仲間や学習コミュニティの存在なんです。一人で頑張るのも素晴らしいですが、仲間と一緒に進むことで、学習はもっと楽しく、そして豊かになることを私は身をもって体験しました。
オンライン読書会でモチベーションを維持
最近は、オンラインで気軽にドイツ語の読書会に参加できる機会が増えていますよね。私もいくつかの読書会に参加しているんですが、これが本当にモチベーション維持に繋がっています。参加者それぞれが選んだ本を持ち寄って、内容についてドイツ語で話し合ったり、お互いの読書進捗を報告し合ったり。時には、ネイティブの先生がファシリテーターを務めてくれる読書会もあって、彼らの視点から作品の背景や表現のニュアンスを教えてもらえるのは、何よりの学びになります。一人ではなかなか読み切れないような長編小説も、みんなで「ここまで読もうね!」と目標を共有することで、不思議と頑張れるんですよね。それに、他の参加者さんがどんな本を読んでいるのかを知ることで、新しい本との出会いにも繋がるし、「みんな頑張ってるんだから私も!」という良い刺激になります。孤独な学習ではなく、みんなで一緒に「ドイツ語の森」を探索しているような感覚は、本当に楽しいですよ。
アウトプットの場としても最適!読書で深まる交流
読書会は、ただ本の内容について語り合うだけでなく、ドイツ語のアウトプットの場としても非常に優れています。読んだ内容について自分の意見を述べたり、登場人物の心情を推測して話したりする中で、自然とドイツ語を「使う」練習ができるんです。私も、最初はうまく自分の意見をドイツ語で表現できずにもどかしい思いをしましたが、回を重ねるごとに少しずつスムーズに話せるようになりました。参加者の中には、ドイツ語学習歴が長い先輩方もいらっしゃるので、彼らの流暢なドイツ語を聞くことは、リスニング力アップにも繋がりますし、表現の引き出しを増やす良い機会にもなります。そして何より、共通の趣味を持つ仲間とドイツ語で深く交流できるのは、語学学習を続ける上での大きな喜びです。読書を通じて、言語だけでなく、人との繋がりも深まるというのは、本当に素晴らしい経験だと感じています。
ドイツ語原書読破への道のり、私の失敗談と成功体験
どんなに素晴らしい学習法やツールがあったとしても、実際にドイツ語の原書を読み続ける道のりは、決して平坦なことばかりではありません。私自身、これまでたくさんの失敗を経験してきましたし、「もう無理!」と投げ出したくなったことだって数えきれないほどあります。でも、その一つ一つの失敗や挫折があったからこそ、今の私がいるのだと強く感じています。大切なのは、失敗を恐れずに挑戦し続けること、そして小さな成功体験を積み重ねていくことです。ここでは、私のリアルな読書体験から得た、とっておきのヒントをシェアさせていただきますね。
最初は「読めない!」と嘆いた日々
初めてドイツ語の原書を手に取った日、「よし、これでドイツ語マスターだ!」なんて意気揚々としていた私ですが、現実は甘くありませんでした。最初の数ページで、知らない単語の洪水、複雑すぎる文構造、そして全く頭に入ってこない物語…。正直、「これ、本当に読めるようになるのかな?」って、かなり絶望しました。辞書を引いても、その単語がこの文脈でどう使われているのかがピンとこなくて、一文を理解するのに何分もかかってしまう。読み進めるどころか、前に読んだ内容すら忘れてしまう始末で、まさに「読めない!」と嘆く日々でした。あまりにひどい時は、本を閉じて「もう今日はいいや…」と、そっと棚に戻したことも何度もあります。今思えば、あの頃は「完璧に理解しよう」としすぎていたんですよね。完璧主義が、私自身の首を絞めていたわけです。
小さな成功体験が次のステップへ導く
そんな挫折の淵にいた私を救ってくれたのは、まさに「小さな成功体験」でした。ある時、「今日はこの章だけは読み切ろう!」と目標をぐっと下げて、辞書を引く回数も意識的に減らして、とにかく「最後までたどり着く」ことを優先してみたんです。そうしたら、多少曖昧な部分はあっても、なんとか章の終わりまで読み終えることができたんです!その時の「やった!」という達成感は、それまでの挫折感を吹き飛ばすほどのものでした。そして、その達成感が、次の章へ、次の本へと私を導いてくれる原動力になったんです。一冊をまるごと読破できなくても、「このページは理解できた」「このフレーズはすごく綺麗だな」といった、本当に些細なことでもいい。自分自身が「できた!」と感じられる瞬間を大切にすること。それが、ドイツ語原書読解を長く続けていく上での一番のご褒美になるはずです。焦らず、自分のペースで、一歩ずつ進んでいきましょう!
最後に
これまでの道のりを振り返ると、私も何度も壁にぶつかり、くじけそうになったことがありました。でも、ドイツ語の原書を読むという経験は、想像以上に多くの喜びと学びをもたらしてくれましたね。言語学習はマラソンのようなもの。すぐに結果が出なくても、諦めずに一歩ずつ進んでいけば、必ず新しい景色が見えてきます。この記事が、皆さんのドイツ語読書ライフをより豊かにするヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。さあ、あなたも自分だけの「宝物の一冊」を見つけに、ドイツ語の世界へ飛び込んでみませんか?
知っておくと役立つ情報
1. 最初の1冊は、迷わず自分のレベルに合ったものを選びましょう。背伸びしすぎると挫折のもとになります。絵本や児童書、学習者向けのリーダーから始めるのが、成功への近道です。特に、すでに内容を知っている物語のドイツ語版は、ストーリーを追いやすく、単語の推測もしやすいのでおすすめです。
2. 辞書は「賢く」使いましょう。知らない単語が出てくるたびに全てを引くのではなく、まずは文脈から意味を推測する練習を。本当に重要な単語や、何度も出てくる表現だけを重点的に調べると、読書のリズムを保てます。電子辞書や翻訳アプリをうまく活用すれば、時間を大幅に節約できますよ。
3. 「多読」と「精読」をバランス良く取り入れるのがおすすめです。ざっと大意を掴む多読で全体の理解度を高め、お気に入りの箇所や重要な部分は精読で深く掘り下げてみてください。私自身、このメリハリをつけることで、飽きずに長く続けられるようになりました。気になる表現はノートに書き出すのも良い方法です。
4. デジタルツールとアナログの良さを両方活用しましょう。電子書籍の辞書機能は時短に繋がり、文字の拡大も自由自在。一方、紙の書籍はページをめくる喜びや、書き込みや付箋で自由にカスタマイズできる楽しみがあります。気分や状況に合わせて使い分けることで、読書がもっと快適になりますよ。
5. 読書仲間を見つけたり、オンラインの読書会に参加したりするのも非常に効果的です。一人で抱え込まず、疑問を共有したり、感想を語り合ったりすることで、モチベーションが維持でき、学習効果も飛躍的に向上します。他の人が読んでいる本から新しい発見があることも少なくありません。
重要ポイントまとめ
ドイツ語の原書読解は、ただ単語や文法を覚えるだけではない、まさに「生きた」言語を学ぶ最高の機会です。最初は難しく感じるかもしれませんが、自分に合った本を選び、完璧を求めすぎずに読み進めることが何よりも大切。そして、辞書との賢い付き合い方や、多読と精読のバランス、デジタルツールの活用、さらには読書仲間との交流を通じて、あなたのドイツ語力は想像以上に伸びるでしょう。何よりも、読書を通じてドイツの文化や人々の思考に深く触れる喜びは、かけがえのない経験となります。焦らず、自分のペースで、この素晴らしい旅を楽しんでくださいね。きっと、新たな発見と感動があなたを待っていますよ。この経験は、語学力だけでなく、あなたの世界観を豊かにしてくれるはずです。
よくある質問 (FAQ) 📖
質問: ドイツ語原書を読むのが初めてなのですが、どんな本から始めれば良いですか?
回答: ドイツ語の原書に初めて挑戦する方、最初は「どんな本を選べばいいんだろう?」って迷いますよね!私も最初はそうでした。でもご安心ください。いきなり難しい文学作品に挑む必要は全くありませんよ。私のおすすめは、まずは「児童書」や「多読用のやさしいレベルの読み物」から始めてみることです。物語がシンプルで、使われている単語や文法も比較的易しいので、抵抗なく読み進められます。例えば、エーリッヒ・ケストナーの作品なんかも、ユーモアがあって心温まる物語が多いので、ドイツ語学習初期の頃にすごく楽しんで読んだ記憶がありますね。 大切なのは、「読んでいて楽しい!」と感じられるかどうか。内容に興味を持てれば、多少わからない単語が出てきても、辞書を引くのも苦にならないものです。まずは、図書館で借りてみたり、電子書籍で気軽に試し読みできるものから探してみるのも良いでしょう。 自分のレベルに合った一冊を見つけることが、ドイツ語読書を続ける一番の秘訣ですよ!
質問: AI翻訳ツールも進化した今、それでもドイツ語原書を読むメリットって何ですか?
回答: 「AI翻訳がこんなに便利なのに、わざわざ原書を読む意味ってあるの?」って思う気持ち、すごくよく分かります!でもね、私の経験から言うと、原書でしか得られない「かけがえのない体験」が確かにあるんです。 AI翻訳は確かに内容を理解する手助けをしてくれますが、それはあくまで「情報」としての言葉。原書を読むと、著者が込めた感情、ユーモア、皮肉、そしてその国の文化や人々の思考パターンまで、まるでその場で会話しているかのようにダイレクトに伝わってくるんです。 これは、単語を覚えるだけでなく、文脈の中で「生きたドイツ語」のニュアンスを掴むことができるからこそ。 私も、原書を読み進めるうちに、単語一つ一つの意味だけでなく、その言葉が持つ背景や、著者の繊細な心の動きを感じ取れるようになり、それが驚くほど会話力の向上にも繋がったのを実感しています。 AIでは決して再現できない、言葉の奥深さや味わいを、ぜひあなたにも体験してほしいですね。
質問: ドイツ語原書を読む中で、途中で挫折しないための良い方法はありますか?
回答: ドイツ語原書を読んでいると、「うわ、全然わからない…」「もう無理かも…」って、私も何度も壁にぶつかりました。でも、そこで諦めないための「コツ」があるんです! まずは、完璧を目指さないこと。 すべての単語を理解しようとするのではなく、「全体の50~60%くらい分かればOK」という気持ちで、ざっくりと読み進めてみてください。 わからない単語は、その都度辞書を引くのも良いですが、まずは物語の流れを止めずに読み切り、後でまとめて調べたり、文脈から推測する練習をするのも効果的です。 私が効果的だと感じたのは、日本語訳がある本なら、一度日本語で内容を把握してから原書を読む方法です。 これだと、ストーリーの全体像が頭に入っているので、知らない単語が出てきても混乱しにくくなります。また、読書ノートを作って、印象に残った表現や単語を書き留めておくと、後で見返した時に「こんな表現があるんだ!」と新しい発見があって、モチベーション維持にも繋がりますよ。 そして何より、一番大切なのは「楽しむこと」です! 自分が心から面白いと思えるジャンルや作家を見つけることが、長く続けるための最大の原動力になりますからね。